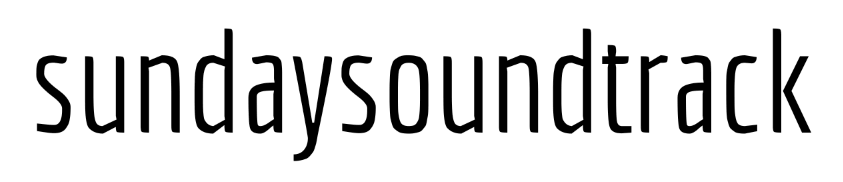そこは、一年の半分以上の日が曇りと雨というところだった。たとえ朝がどんなに雲一つなく晴れていても、午後になれば当たり前のように真っ黒な雲が広がってきて土砂降りになってしまうような、そんなところだった。自転車で通勤していた僕は、スーパーで買った安物のビニールのレインコートを通勤鞄に忍ばせていたし、外出先での不意の雨に仕方なく買ってしまった透明なビニール傘も、5本もたまってしまった(レインコートでは困るときもあるのだ)。晴れているからといって、休日に布団を干したまま外出することも一種の賭けだった。
とにかく毎日がどんよりとして、太陽の光が恋しい、そんなところだった。
当時僕が働いていたところのすぐ裏側には、細い川が流れていた。空気はきれいな街だったので、その川も都会に比べたらきれいなものだった。ただ困ったことに、その周辺には「鼠」が多かった。
僕の働いていたところは食品を扱っていた。そして、その建物があまり新しいものでなかったために「鼠」がよく出入りした。きっと僕達の知らない穴から入ってくるのだろう。「鼠」はどこからともなく現れた。もしかしたら建物に住み込んでいたのかも知れない。
その「鼠」は、夜11時を過ぎた頃から活動を開始した。大抵は姿を見せずに、「チューチュー」という鳴き声や「ガサゴソ」という物音で僕達に存在を示した。「鼠」は僕達が帰った後に仕事をするのだ。朝になれば、袋が噛み破られて散らばってしまった米粒や、囓りかけのクラコットの残骸が床に残っているのを僕達は目にすることになった。
警備会社の人にも何度か迷惑をかけた。どうやらセキュリティ・センサーに「鼠」が引っかかるらしいのだ。その「エラー」のために、警備会社の人に何度か無駄足を踏ませてしまった。そして、「鼠」のために無駄足を踏ませてしまった彼らに対して、僕達は手数料を支払わなければならなかった。やれやれ、「鼠」が存在しているだけで、経済はまわってしまう世の中なのだ。
警備会社の人も「鼠」如きでわざわざ出向くのも嫌なのだろう、センサーが「鼠」に反応しないように改良してくれた。僕達としても、エラーの度に「なんだよ、また『鼠』かよ」と警備の人に思われていると、いざ本当にオオカミが現れたときに困るのでそれはそれでありがたかった。無駄金も支払わなくて済むならそれにこしたことはない。
「鼠」には本当に手を焼いた。散らばった米の掃除は大変だったし、ゴミ箱も荒らされた。ある時は冷蔵庫の電線を囓られて冷蔵庫が止まってしまったし、ある時は休憩室の鞄を荒らされたりもした。
僕達は、ホームセンターで「鼠取り」を2つ買ってきて、片っ端から「鼠」を捕まえることにした。「鼠」がどれぐらいいるのか見当もつかなかったけれど、とにかく「鼠」は僕達にとってはただただ苦悩の種であり、ただただ厄介だったのだ。
その「鼠取り」は、籠の中に餌を入れて、「鼠」がそれを取ろうと中に入ったら扉が閉まるという、原始的な造りのものだった。これぞまさに「鼠取り」といった感じのものだ。僕は試しに自分の腕をその籠の中に突っ込んでみたら、強烈な痛さを伴って僕の腕は見事に扉に挟まった。うむ、これなら強力な助っ人になってくれるだろう。
餌にはチーズや焼いたジャガイモを使った。迷惑な「鼠」如きに値の高いチーズを使うのは少々悔しかったが、それでも「鼠」が引っかかるなら良しとした。そして、それを「鼠」が通りそうな場所に仕掛けた。
朝9時に仕事場を開けるのは、大抵僕の役目だった。一日の出勤スケジュールに「早番」と「遅番」があって、多くの場合僕が「早番」だったからだ。その「鼠取り」を仕掛けた翌朝、僕は入り口の鍵を開けてセキュリティを解除し、そして真っ先に「鼠取り」の場所へ向かった。妙な感覚の期待を心に抱きながら。しかし、「鼠」はかかっていなかった。餌も取られていなかった。「鼠取り」の位置すら少しも変わっていなかった。そう簡単に「鼠」は捕まらないのだ。トムとジェリーの話がそうであるように。世の中がそうであるように。
餌を若干増量したそのまた翌朝、入り口の鍵を開けてセキュリティを解除したとき、僕の耳に「鼠」の声が聞こえた。「やった!」 僕は急いで「鼠取り」の場所に向かった。見事に灰色の「鼠」が1匹捕らえられていた。挟まれてしまったのだろうか、ピンク色の尻尾がちぎれて「鼠取り」の外に転がっていた。「鼠」は僕に向かって威嚇するように「チューチュー」と鳴いていた。
いや、もしかしたら「鳴いていた」のではなくて、「泣いていた」のかも知れない。
さて、この「鼠」をどうしよう。目的は「鼠」退治だったわけだから、やっぱり殺してしまわないといけないのだろうか。うむ。でも、一体どうやって殺すのだ? 捕らえたはいいが、この体長20センチはあるだろう「鼠」を(体長は尻尾は除いた長さ。そもそもコイツは尻尾が取れてしまっているのだが)、これからどうすればいいのだ? 火あぶりか、もしくは水攻めか、あるいは毒殺か。なんだか残酷だな。
昼過ぎまで考えた結果、僕は「尻尾が取れてしまった」ことを釈放理由にして、その「鼠」を川に流すことにした。僕は「鼠取り」の籠をぶら下げてコンクリートの川縁まで行き、扉を開けて「鼠」を川に逃がした。尻尾がなくても上手く泳げるのかどうかよくわからなかったけれど、とにかくその「鼠」は逃げるようにして川を流れていった。とりあえずそれで、僕は一件落着とすることにした。尻尾はつまんでゴミ箱に捨てた。
もちろん、「遅番」の上司には責められた。何故殺さなかったのだと。そりゃもちろん「鼠」は僕達にとって迷惑なものだということは僕にも十分わかっていた。確かにほとほと困ってる。でも、朝ここに一番に来るのは大抵僕なんですよ。僕が殺さなきゃいけないんですよ。
結局、次に捕まえたときには、大きな発泡スチロールに水を溜めて、そこに籠ごと沈めて水死させることになった。できるだけ無惨な死に方はさせたくなかったけれど、火あぶりや毒殺よりかはよっぽどマシな方法だった。僕の頭では、それ以上の方法を思いつけなかった。
その翌朝、入り口の鍵を開けた僕の耳に再び「鼠」の声がした。「鼠取り」に引っかかっているのだ。昨日の「やった!」というような達成感もなく、妙な感覚の期待もなく、少々重い気持ちで僕は「鼠取り」の場所へと向かった。昨日と同じぐらいの大きさの「鼠」が、同じように「チューチュー」鳴きながら僕に向かって威嚇していた。「鼠」2号。ただ昨日と違ったのは、その「鼠」2号には尻尾があったということだった。床に尻尾が転がっていなかったことは、重たかった気持ちを5グラムほど軽くした。でも、まだその気持ちは1500グラム近くもあるのだ。やれやれ。
僕はできるだけ何も考えないようにして、準備してあった発泡スチロールに水を溜めた。水道の水が勢いよく発泡スチロールに落ちていくのを眺めながら、重たそうなその水音で「鼠」の鳴き声を掻き消けそうとした。そして、とても冷静な気持ちだった。
「鼠取り」が十分浸かるぐらいの水を張り終え、僕は何も考えないようにして「鼠取り」を持ち上げてその発泡スチロールの水に沈め、そしてきっちりと蓋を閉めた。その一連の動作をするのに、僕は脳が思考回路に一切の信号を送らないように気をつけていた。ただ僕は、右手で籠を発泡スチロールに入れただけなのだ。それは籠で、それは発泡スチロールなのだ。それは「鼠」で、それは水なのだ。そして僕は休憩室に向かい、スーツを脱いでいつもの作業服に着替えた。
たぶん、そのときの僕の顔は全然魅力的でなかっただろうと思う。別に今の普段の僕の顔が魅力的だと言うつもりはないけれど、そのときの僕の顔を見て好意的な感情を抱く人はあまりいなかっただろうし、付き合っていた彼女なら「あれ? こんな人だったっけ?」と思ったかも知れない。そして、確信はないけれど、そのときの僕の顔は嫌悪感を抱くような顔でもなかったと思う。ただ「魂」の抜けたような、無表情で無機質な顔。学校の理科室の標本になってガラスケースに収まっていそうな、一切の感情移入もできないような顔。
僕は着替えを済ませ、発泡スチロールのある場所に向かい、発泡スチロールの蓋を取った。そして再び何も考えないようにしながら、沈んでいる「鼠取り」を引き上げた。息絶えてしまった「鼠」は水を含んで、先ほどよりも幾分重いような気がした。でも僕は、その籠の重さについては考えないようにした。それは「鼠取り」で、それは「鼠」なのだ。
僕は水道の流しで「鼠取り」の扉を開け、中の「鼠」を取り出し、二重にしたビニール袋にその「鼠」を素早く入れ、そしてその口を堅く結んだ。あくまで事務的に、まるでいつもやってる仕事のように淡々とそれを片付けた。そして、その「鼠」の入った袋をゴミ箱に捨て(確かにこれをゴミ箱に捨ててしまっていいものかどうか、3秒ほど躊躇したが)、発泡スチロールの水を捨てた。僕はガス栓をひねって洗浄機の電源を入れ、その発泡スチロールをそのまま洗浄機にかけた。洗浄機のまわる「ゴーッ」という重い音がいつもの朝の仕事の開始を告げ、それから僕はいつものように朝の仕事を黙々とこなした。それは一日のうちの朝であり、一年のうちの一日なのだと、思うことなく感じながら。
その後、僕は同じようにして何匹かの「鼠」を無機質に殺した。尻尾のちぎれてしまった「鼠」もいたし、今にも尻尾のちぎれそうな「鼠」もいた。30センチほどの大きな「鼠」もいたし、暴れて仕方ない「鼠」もいた。でも、そのときその朝の僕にとっては、皆すべてただの「鼠」にすぎなかった。発泡スチロールに籠を沈めることは、そのときの僕にはただの「行為」でしかなかった。
—
一年の半分以上が晴れの日という土地にいる今、あのときの「行為」を振り返ってみると、もっと他に良い方法がなかったものだろうかと思う。もしかしたら今でもその「行為」は繰り返されているのかも知れないし、あるいはそれを解決する新しい方法が見つかったかも知れない。でも、それはもう今の僕には関係はない。
「鼠」を発泡スチロールに沈めたあの日の朝、空が晴れていたかどうかよく覚えていない。でも、あの街の空気はどんよりとしてあまり好きにはなれなかった。
—
もし「鼠」の世界に「鼠裁判」があるとしたら、僕は満場一致で極刑を言い渡され、水攻めの刑の末、「鼠」の餌になってしまうことだろう。「チューチュー」という鳴き声を聞きながら、あのときの「行為」を悔やむだろう。
僕がディズニーランドに行きたがらないのは、つまりそういう訳である。
—
あとがき(あるいは言い訳)
小説というものを今まで僕は書いたことがないし、書こうと思ったこともなかったので、これが僕の初めての「短編小説」になるのかも知れない。最初はある日の日記のつもりで書いていたのに、脚色してしまって気がつけばこんな文章になっていた、そんな感じだ。文体も、ある作家の影響が見え見えで自分でも閉口するし(やれやれ)、稚拙であまり誉められたものではないとは思う。
まあ、記念として。
あと、原稿用紙に向かって書いたわけではないので、ある程度ウェブ上のテキストの書き方に準じて書いた。その辺の不備は勘弁を。