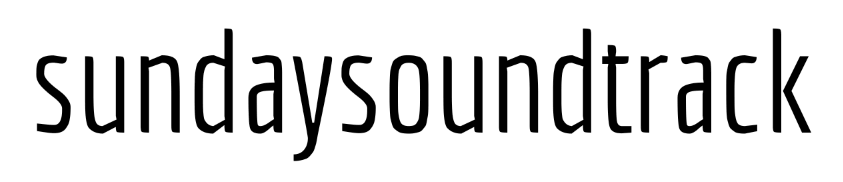広告– tag –
-

「日本のグラフィックデザイン2013」を見た(2013年7月28日)
2013年7月28日、六本木に移動して、東京ミッドタウンで開催されている「日本のグラフィックデザイン2013」へ。書籍とか商品パッケージとか、広告ポスター、ロゴ、その他諸々の「デザイン」の展示。 -

2013年6月8日、世田谷美術館へ「暮らしと美術と髙島屋」展を見に行ってきた
2013年6月8日、世田谷美術館へ展覧会「暮らしと美術と髙島屋」展を見に行ってきた。高島屋百貨店の、創業1831年からの「美術」に対する取り組みをまとめたもの。とてもおもしろかった。 -

小田急電鉄の広告「代々、夏は家族のものだった。」
「代々、夏は家族のものだった。」というコピーの、箱根旅行の小田急電鉄の広告。3月にも、「春を、ご用意しました。」というコピーで僕は「うわー」とやられているんだけど、この夏向けの旅行のコピーもいいなあ。 -

ホテルのドアサイン(ドン・ディス カード)に似せた本の栞
ホテルのドアサインの形をした、本の栞。紀伊國屋書店で本を買ったらついてきた。 -

「春を、ご用意しました。」小田急
「春を、ご用意しました。」というコピーの、箱根旅行の小田急電鉄の広告。すごく普通で飾らなくて素直すぎるコピーなのに、これ以上ない定番の写真をもって「ご用意しました。」と言われて、すごく行きたくなった。 -

西友にあるウォルマートのロゴのポスターにちょっと違和感
西友がこのところウォルマート色を強く出していて、ウォルマートの買い物バッグとかを前から売ってたけど、店内のポスターもウォルマートのロゴが前面に出たものになってた。ちょっと違和感。
1