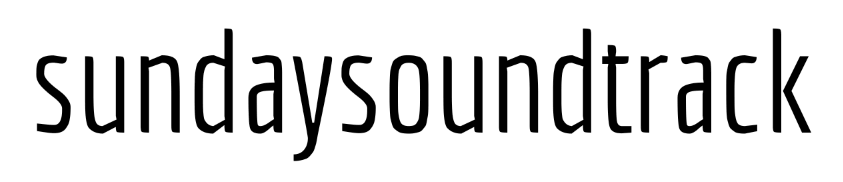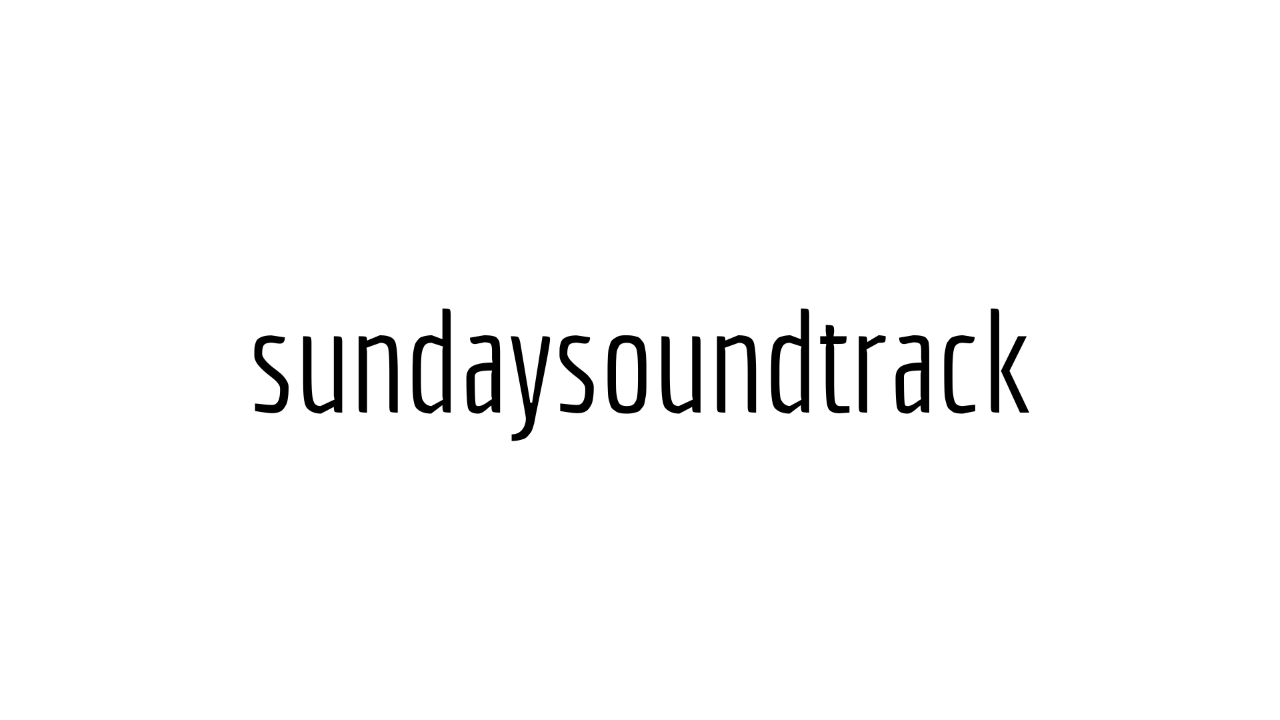その1 (2001/01/26)
「カタン」とミニ・コンポの電源が入ってFM放送が流れ出した。それから1、2分すると、今度は目覚し時計が鳴り始める。賢いのか鬱陶しいのかよくわからないけれど、この目覚し時計は3分毎に鳴るようになっている。僕は3分毎に鳴る目覚し時計をその都度止め、FM放送を右の耳から左の耳に澱みなく流すように聴いていた。どんな曲が流れているのかは覚えていない。ニュースや天気予報も忘れてしまった。
低血圧なのだ。
30分ほどしてやっと体を起こす。エアコンのリモコンを手にとり、スイッチを入れて暖房を入れる。頭が起きていなくても「部屋が寒い」ということはどうやら理解できているようだ。FM放送を相変わらず右の耳から左の耳に流しながら、僕は服を着替える。外はどうやら曇りだ。
ボーっとした頭のまま、冷蔵庫から牛乳を取り出してマグカップに注いだ。そしてそのマグカップを電子レンジに入れ、1分30秒にセットしてスタートボタンを押した。1分30秒という時間は、何度も実験を繰り返して得られた、僕にとって最適のホットミルクを作り出すレシピだ。僕はホットミルクができる間に顔を丁寧に洗った。顔を洗ってタオルで拭き終わると、タイミングよくホットミルクが出来上がるようになっている。僕はマグカップをテーブルの上に置き、7個入りロールパンの袋を開けた。
朝食はキチンととるほうだ。「パン派」である。別にこだわってる訳じゃないけれど、物心ついた頃からずっと朝食はパンだったのだ。ただの習慣である。
ロールパンを1個齧ったとき、妙なことが起きた。マグカップのホットミルクのほんのかすかな湯気が、何か白い「雲」のようなものを形成し始めたのだ。「雲」はすぐに卵くらいの大きさになり、手足が生えて小さな人間のような形になった。あっという間の出来事だった。
ロールパンを齧ったままびっくりして眺めていると、その人間の形をした白い「雲」が僕に向かって喋りだした。
「ねえ、どこに行きたい?」
寝ぼけた目で見ていたから気が付かなかったけれど、よく見たらその「雲」は天使のようだった。ちゃんと背中に小さな羽もあるし、頭の上には輪がある。でも、手に持っているのは弓矢じゃなくてどうやら牛乳瓶だ。牛乳瓶には可愛いストローが挿してあった。
牛乳瓶?
ロールパンを齧ったままの僕を見て、その天使は僕にまた喋りかけてきた。
「ねえ、どこに行きたいの?」
まだ頭がきちんと働いていなかったので、僕は何を喋っていいのかよくわからなかった。そもそもこの事態がうまく飲み込めなかった。これは夢の続きのような気がした。
僕は齧ったロールパンをとりあえず無理やり飲み込んだ。マグカップのホットミルクを今飲んではいけないような気がしたので、喉が詰まりそうだった。そんな僕を見ながら、天使はもう一度聴いた。
「ねえ、どこに行きたいの?」
この天使は願い事を叶えてくれる天使なんだろうか。ふとそう思ったけれど、この天使はどうやら「場所」限定のようだ。場所限定の願い事って、そんなのありか?と思ったけれど、自分が今どこに行きたいのか、そんな質問を突然聞かれても困る。でも天使は僕を見ていた。僕は何か答えなければいけなかった。
「と、とりあえず、会社かな」
そう思っていたわけじゃないけれど、ふと口をついて出た言葉がそれだった。別に会社に行きたい訳じゃない。行かなければいけないことになってるんだ。
「ふーん。それじゃあ何にも変わんないね」
天使は首をかしげてそう言った。そして僕の右手に持っているロールパンを欲しそうに少し眺め、それからすーっと僕のマグカップのミルクの中に消えていってしまった。あとには何も残らなかった。ホットミルクからはかすかな湯気が立っていたし、僕は自分の部屋のテーブルの前に座ったままだった。試しに5秒ほど目を閉じてゆっくりと目を開けてみたけれど、やっぱり自分の部屋だった。
FM放送はバーゲンズの「ジンセイ」を流していた。寝ぼけた僕の耳には奥居香が歌っているように聞こえた。
—
その2 (2001/02/08)
ホットミルクの天使が現れたあの日から、気のせいか朝の目覚めがよくなった。なんだか布団の中でそわそわしてしまうのだ。おかげでFM放送でかかっている曲が判別できるようになったし、DJのトークもニュースも天気予報もバッチリである。朝会う人に、新しいニュースを聞かせてやりたいくらいだ。
でも、天使が現れたのはあの日だけである。あれからもう2週間が経つ。人に話すと間違いなく「夢だよ」と済まされてしまうので、もちろん誰にも喋っていない。確かに全く夢みたいな話だけど、僕は夢ではなかったと確信している。わざわざそのFM放送局に、あの日のあの時間にバーゲンズの「ジンセイ」がかかっていたかどうか確認したくらいだ。間違いない。今月の僕の給料を賭けてもいい。
今思い出してみると、バーゲンズの「ジンセイ」は暗示的であったような気がしてくる。天使は「ねえ、どこに行きたい?」と聞いてきた。僕はどこに行きたいのだろう。あのとき咄嗟に答えた「会社」ではないことは確かだ。
僕はどこに行きたいんだろう。
確かに、人生はまだまだこれからだ。
朝が来るたび、僕は顔を洗うのもそこそこに、どきどきしながら電子レンジでホットミルクを作る。そしてロールパンやスティックパンやクロワッサンやサンドイッチなどを齧りながら、マグカップのホットミルクから立つほんのかすかな湯気を凝視する。何かが起きるかもしれないのを、じっと待つ。そしてその日のパンを全部食べ終わり、ホットミルクからもう湯気が立っていないのを確認してから、おもむろにホットミルクを飲む。少し冷めてしまっているのだけれど、そうしない訳にはいかないのだ。
もしかしたらあの質問の答え、つまり僕がどこに行きたいのかが決まったら、天使は僕の目の前に再び現れてくれるのかも知れない。
ねえ、どこに行きたい?
どこだろう?
—
その3 (2001/03/04)
バターロールはやっぱり「卵白をたっぷり塗りました」と言わんばかりの「てかり」を発しているものが美味しそうである。スーパーで袋詰になって6個入りとかで売られているものの多くは、この「てかり」が若干弱いような気がする。やっぱりパン屋さんで焼いたものにはかなわない。
そんな「てかった」バターロールを齧りながら、今日もまたホットミルクを飲む。1月に出会った天使はやっぱり夢だったのかもしれないと、最近は思うようになってきた。それでも、ホットミルクを電子レンジで作るときの時間を1分30秒から1分45秒にしてみたりと、くだらない努力をしてみたりもする。15秒長くすると、その分ホットミルクから立つ湯気が多くなる。
これから段々と気温も上がってきて、別にホットミルクをわざわざ作らなくてもいいくらいの暖かさになるんだろう。そうだ、もう3月なんだ。あの時はまだ冬真っ盛りだったけれど、あっという間に陽射しが春になってしまった。FM放送の天気予報は、最高気温が徐々に上がってきていることを告げていた。天気予報が終わり、いくつかCMが流れ、それからエリック・クラプトンの新曲がかかった。スティーヴィー・ワンダーのカヴァーらしい。
気が付くと、マグカップに天使が腰掛けていた。
天使はこの前と同じように左手に牛乳瓶を持ち、何か鼻歌でも歌っているような感じで体でリズムをとりながら僕を見上げていた。足をぶらぶらさせているのがかわいい。
僕は少しだけびっくりして小さく声をあげた。マグカップを凝視するのも慣れっこになってきて、「今日もどうせ現れないよな」とつい考え事をしてしまうので、「おお、気がつけばこんなところに」といった感じの現れ方だった。マグカップからの湯気が「雲」を形成しかどうかには全然気がつかなかった。
「あ、あのさ、いつからそこにいるの?」
「ん? さっきから」
結構あっさりと答える。どうやら天使は、ラジオのエリック・クラプトンにリズムを合わせてるようだった。僕は聞いてみた。
「ラジオ聴いてるの?」
「うん」
「この曲歌っているの、誰だか知ってる?」
「エリック・クラプトンだろ?」
…。あっけなく答えられてしまった。天使の世界がどんなものなのかよく知らないけれど、少なくともこの天使はエリック・クラプトンを知っているらしい。やれやれ。
「ねえ」、と今度は天使が聞いてきた。「エリック・クラプトンの新しいアルバムって『Reptile』って言うんだろ? どうしてそんな変なタイトルつけるんだろうね」
…。なんだこいつ、やけに詳しいな。『Reptile』か。きっとエリック・クラプトンは変な奴なんだろう。
「ねえ」 天使が続けて聞いてくる。
「昔、何になりたかった?」
…。何になりたかった? それって、こないだの質問「どこに行きたい?」の次の質問なんだろうか? ということは、あの質問は終わったのだろうか? あれからずっと僕はどこに行きたいのか考えていたのに。
「エリック・クラプトンみたいにギターが弾けたらなあとか、思わなかった?」
「ううん」 僕はちょっと答えに詰まった。
「ううん、エリック・クラプトンみたいに弾けたらなあとかはあんまり思わなかった。指が短いから最初っからギターは上手くなるの諦めてたし。…。でもミュージシャンにはなりたかった」
「ふうん」
「でも、…なれなかったけどね」
僕は肩をすぼめてみせた。でも天使は僕をじっと見ていた。体でリズムをとりながら。
「ギターは弾けるんでしょ?」
「弾けるけど上手くないよ」
「でも弾けるんでしょ?」
「コードしか弾けないよ」
「でも弾けるんでしょ?」
「…。うん。でも、だから下手だけどさ」
どうしてこんな言い訳みたいな言い方をしてしまうんだろう。僕は少し汗をかいているようだった。天使はじっと僕を見ていた。なんだか尋問されているような気分だ。
「ギターが弾けるんだったらそれでいいじゃない」
「…。なにが?」
「弾けるんでしょ?」
「弾けるけど、下手だよ」
「でも、ギターが弾けたらミュージシャンじゃない」
「ううん、そんなたいそうなものじゃないよ」
「ギターが弾けたら音楽ができるじゃない」
「ううん、でもたいした音楽じゃないよ」
「でも音楽じゃない」
「…。そりゃ音楽だけどさ」
「自分で曲とか作ってたの?」
「作ってたけど、…でもだからたいした曲じゃないよ」
「でも、音楽なんでしょ?」
「…。そりゃ音楽だけどさ」
「これはエリック・クラプトンの音楽だけど、それは君の音楽なんでしょ?」
「…。」
「じゃあミュージシャンじゃない」
…。正論だ。クオリティというか、レベルとしてエリック・クラプトンと同等に値するかどうかは別として、確かにある種の音楽だ。ミュージシャンと言われるとそれはちょっと違うと思うけれど、ミュージシャンの端くれの出来損ないの、それまた落ちぶれぐらいかも知れない。
エリック・クラプトンの新曲が終わり、DJ は次にウルフルズの「明日があるさ」を紹介した。天使との会話はそこで一旦途切れ、僕達は黙って「明日があるさ」をしばし聴いていた。僕は右手に持ったパンを食べることすら忘れていた。天使はリズムをとるのをやめていた。
「この曲、好きじゃない」、と天使は言った。「なんか、がんばってるのを自慢してるみたい」
「うん。…。僕もあんまり好きじゃない」
「どうして僕はがんばってるんだろう、って口にして言っちゃあ駄目だよね」
「…。そうだね」
うん。なるほど。何かに一生懸命になっているときに「どうしてこんなに一生懸命になってるんだろう」と思うことって、確かにあまりないような気がする。あるとすれば、それは何かの弾みでその「一生懸命さ」に醒めたときだ。そこから再び熱せられることはまずない。そうでなければ自己陶酔だ。
「ねえ、食べないんならパンちょっと貰っていい?」
「え? あ、ううん。いいよ」
そうだ。僕は朝食のパンを食べていたんだ。天使はマグカップからひょいと降りて僕の右手のパンをほんの少しちぎり、マグカップの淵にまたひょいと座ってそのパンのかけらを食べた。そしてストローで自分の左手の牛乳瓶のミルクを飲んだ。僕も食べかけのロールパンの続きを食べた。天使がマグカップに座っているので、ホットミルクは飲めなかった。
「ごちそうさま」と言って、天使がマグカップから立ち上がった。
「あ、えーと、あのさ」
僕は天使を呼び止めた。天使がどこかに帰りそうだったからだ。僕は何か聞かなくちゃいけないような気がした。ものすごく大事なことを聞きそびれているような気がした。このまま天使がどこかに帰ってしまったら、次はいつ会えるのかわからない。
でも、何を聞いていいのかよくわからなかった。
天使は「さあね」と言うように視線を斜め上に逸らして首を傾け、口をすぼめて少し笑ってみせた。それから前と同じように、すーっと僕のマグカップのホットミルクの中に消えていってしまった。マグカップからはもう湯気は立っていなかった。きっともう冷めているんだろう。
FM 放送はウルフルズの「明日があるさ」を続けていた。僕は注意深くマグカップを手にとり、中から天使が現れてこないのを少し確認してからホットミルクを少しすすった。案の定それは少し冷めてしまっていた。僕は食べかけのロールパンの残りを口の中に放り込み、時計を見た。7時45分だった。少し急がないといけない。
いつかきっと、誰が何をわかってくれるというんだ?