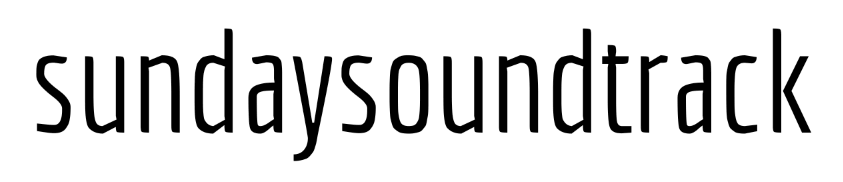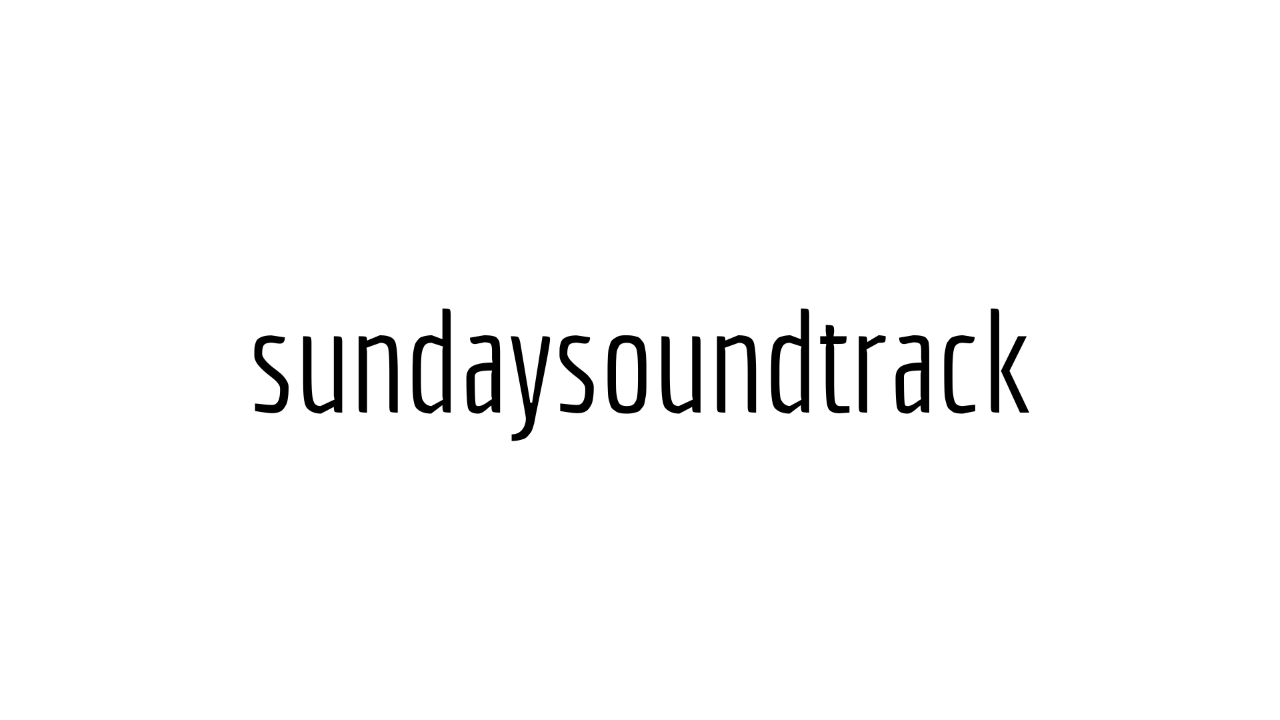「何やってるのよ、早く出てきなさい」
ちょうど僕の後ろで女の人の声がした。ブランドショップや雑貨屋の入る近未来的な佇まいのHビルの1階吹き抜けのところ。ただでさえ人がごった返す土曜日。午後6時にアイドル・グループのイベントが広場で予定されていることもあって、それまでの時間を潰すお客さんで1階の広場付近はいっぱいだった。お客さんと言っても、大半は小学生や中学生や高校生だ。
「何やってるのよ、もう。そんなところに入るからでしょ」
「ううん」と頷いているのか呻いているのか、男の子の声がした。女の人の声はきっと母親なのだろう。僕は別に振り返らなかった。僕はHビルの許可証バッジを胸につけ、「お客様アンケート」を取っていたのだ。今日どのショップに立ち寄っただとか、Hビルにあって欲しいブランドはありますかとか、そういった類のアンケートだ。エスカレーターから降りてくるお客さんの中から人の良さそうな人を選んでは、僕は頭を下げていた。
「何しているの。抜けないの?」
僕はその声でなんとなく振り返った。ちょうど僕はブランドショップのウインドウガラス付近に立って人を選んでいたところだったので、「きっと柱とウインドウガラスの間に子供が入ったんだろう」と思っていたら案の定そうだった。小学1年生か幼稚園ぐらいの男の子だった。
その男の子は頭を挟まれていた。
母親らしき人と父親らしき人が側に立っている。他のお客さんも何人か立ち止まって男の子を見ていた。その男の子は柱とウインドウガラスの間を通り抜けようとしたんだろう。それで頭を入れたはいいけれど、ちょっと通り抜けるには無理かもしれないと思い、戻ろうとしたら頭が抜けなかった。きっとそんなところだ。
スーツを着てHビルのバッジをつけていることもあって、僕はアンケートを中断して「大丈夫ですか」と母親に声をかけてみた。でもすぐに、「ああ、でも大丈夫じゃないですよね」と小さな声で訂正した。困り切ってちょっと泣き出しそうな男の子の顔を見れば、「大丈夫ですか」と暢気なことを言っている場合じゃないことはすぐに判断できた。うん。これは困った。僕はアンケート用紙の入った紙袋を脇に置いた。
僕は男の子の頭を挟んでいる柱をウインドウガラスの反対側に押してみた。うんとも寸とも言わない。当たり前だ。成人男性が押したぐらいでぐらつくような柱は柱じゃない。男の子も一生懸命頭を抜こうとするけれど、頭蓋骨や耳が痛いんだろう、どうしても抜けない。段々と僕らの回りに人が集まりだした。
僕はしゃがみ込んで男の子の小さな手を取り、「大丈夫だからね。心配しないでね。いま助けを呼ぶからね」と声をかけた。男の子の手は小さく、何故か冷たかった。
僕は立ち上がって近くに寄ってきた同僚にガードマンを呼んでくれるよう頼み、そして上着の胸ポケットから携帯電話とHビルに来たときに受け取った書類を取り出した。滅多に来ないところに来て緊急事態が起きると少し困る。僕は3枚ほどの書類をめくり、目に付いた電話番号に電話をかけた。Hビルを管理する百貨店の庶務宛だ。書類を話し口にあてて雑音を遮る。コールは1回。
「はい。○○百貨店○○店庶務課です」
「あ、わたくしHビルで来店客数カウントとアンケートをやっております○○ですけれど、ちょっとお客様の子供が、えー、柱とお店の壁の間に挟まれて抜けなくなりまして、誰かこちらに送っていただきたいのですが」
「えーと、…すいません、少々お待ちくださいか」と庶務課の女の人。
僕らの周りを囲むお客さんの輪が大きくなっている。ざわざわ。
10秒ほど経ち、「もしもし。庶務の○○ですが」と電話の声が男の人に変わった。僕は女の人に喋った内容と同じ内容をもう一度喋った。
「…そちらはHビルですよね。えーと、こちらではよくわからないのでHビルの方にもう一度電話をしてもらえませんか」
「えーと、…でも、私の頂いている書類にはこちらの電話番号しか載っていないんですよ。子供の頭が挟まって抜けないんですよ。ちょっと急いで頂けませんか」
「少々お待ち頂けますか」
その百貨店はこのHビルのすぐ隣だ。それに管理しているのはその百貨店だ。どうして「こちらではわからない」のだ? どうして子供が頭を挟まれているのに待たなければいけないんだ?
周りを見渡しても、まだガードマンは来ていないようだった。男の子は泣き出しそうだった。僕はいったん携帯電話を耳から話し、目に付いたもう一人の同僚に「ちょっと、Hビルの事務所に行ってもらえる? こっちはなんか全然来てもらえそうにないし。あと、誰かにこの辺の交通整理やってもらえる?」と言った。やれやれ。どうしてこう、たらい回しなんだろう。
「もしもし、えーと、そちらHビルですよね」
「あの、ホントに急いでくれますか。そんな、私の所属とかそういったことを言ってる場合じゃないんで」
「…じゃあわかりました。そちらに連絡を入れますので」
「すいません。お願いします」
僕は庶務の男の人が電話を切るのを待たずにこちらから切ってやった。はっきり言うと不快だった。携帯電話を胸ポケットにしまって一呼吸入れ、そしてもう一度しゃがんで男の子の前に座り、小さな冷たい手を取った。
「もうちょっと待ってね。大丈夫だからね。痛くない?大丈夫? 怖くないからね。もうすぐ出れるからね」
程なくして同僚がガードマンを連れて来て、間を空けずにHビルの事務所の男の人が駆け込んできた。説明しなくても状況は判断してくれたようだ。柱とウインドウガラスに頭を挟まれた男の子が、僕と手を繋いでいるんだ。他に何を説明すればいい?
事務所の男の人とガードマンと小さな声で言葉を交わす。「とりあえず、水に濡らしたタオルで周りを濡らして、滑らせるようにしてみましょうか」と事務の人。僕の斜め後ろにいた通りがかりの男のお客さんが口を入れた。「洗剤がいいですよ」 ううっ、洗剤か…。「じゃあ、…んー、…石鹸水で、うん、それにタオルを濡らして。うーん、…それで駄目なら消防署に…」と事務の人。
僕は男の子の手を繋いだままだ。「大丈夫だからね。怖くないからね。もうすぐ助けるからね」 この頃の子供は、いったいどの程度まで大人の会話を理解できるのだろう。
タオルはすぐに届いた。周りはすごい人だかりになっていた。「ちょっとボク、目を閉じて。目を閉じて。怖くないからね。大丈夫だからね。ちょっとだけ我慢してね」と僕。男の子の頭の回りの柱やガラスが濡らされていく。最初は頭にタオルを巻くようにして抜くつもりだったけれど、それは少し無理のようだった。
一通り水浸しにして、もう一度試してみる。僕は男の子の手を繋いでいるので、そういう「押し出す作業」は周りの人に任せていた。「痛いけどちょっと我慢してね。大丈夫だから。すぐに抜けるから」 ふたり掛かりで頭を抜こうとするけれど、男の子が痛がるので少し手こずっているようだ。僕は手を繋いだまま何かを祈った。男の子の痛そうな顔のまま、周りの人は少し強引気味に頭を押した。
ゆっくりと抜けた。
大きな安堵の溜息が出た。周りは目に見えない安堵の溜息でいっぱいになった。人の吐く息に色が付いているとしたら、桃色やベージュやそういった淡い暖かい色の溜息が何十個と浮かんでいたに違いない。
「痛くない?痛くない? 大丈夫? 本当に大丈夫? よくやったね。よかったね」
僕は繋いでいた手を離し、男の子の頭を撫でてやった。男の子は少し緊張して怯えてるようだったけど、それほどどこかを痛がっている様子もなく、どうやら大丈夫のようだ。結局ひとつも泣かなかった。母親は周りに頭を下げている。僕は立ち上がった。やれやれ。
「ほら、もうっ。早くありがとうを言いなさい。もうっ」
男の子は僕に向かって小さく頭を下げた。僕は「よかったよかった」と心の中で溜息をつき、もう一度男の子の頭を軽く撫でた。僕は何も言わなかった。たぶんかけてあげる言葉はあったんだろうけど、僕の頭には何も浮かばなかった。とにかく助かってよかった。男の子の声は聞こえなかったけれど、うつむいたときに小さく何か喋ったかもしれない。
事務所の男の人と母親が何か話をしている。周りの人だかりの輪もゆっくりと散らばり始めた。僕は置いていたアンケート用紙の入った紙袋を持ち、ガードマンと同僚に軽くありがとうを言い、散らばる人だかりの輪と一緒にその場を離れた。アンケートはしばらく中断だ。そんな気分じゃない。
僕はフロアの隅の「Staff Only」と書かれた銀色の扉を押して中に入り、廊下の壁に立てかけてあった折り畳みの椅子を拡げて座った。煙草を吸う人ならここで火をつけるんだろうけど、あいにく僕は煙草は吸わない。僕は上着のボタンを外し、ネクタイを少し緩めて足を伸ばした。喉が渇いた。
—
さて。
僕は男の子の母親がどんな人だったのかを全然覚えていないことに気がついた。もちろん父親もだ。僕がずっと男の子の手を取っていたからかもしれないけれど、あの場面での母親と父親の存在は薄かったように思う(もちろん僕が気づかなかっただけかもしれない)。そもそも男の子の手をずっと握ってやるという役割は、僕ではなくて母親や父親の方がふさわしかったのだろう。でも、誰かがその役割を担わなくてはならなかっただろうし、気がついた僕がたまたまやっていただけだ。僕は母親に替わってあげていた方がよかったのかもしれない。でも、僕にその余裕はなかった。
あの男の子は、頭を挟まれた状態で突然現れた男の人に手を握られて、どんな気分だったんだろう。
そう設問を作ってみたものの、細かいことは考えたくない気分だったので考えるのはやめた。わかるわけがない。それに、その答えを推測考察するのは僕の役割じゃない。
僕はしばらく呼吸を整え、アンケート用紙の入った紙袋を置いたまま扉を押してまた外に出た。あと10分で休憩する時間だけれど、もう別にいいだろう。そもそもアイドル・グループを待つ人だらけで、アンケートなんてほとんど取れやしない。
外に出ると、さっきまでの人だかりはとっくに散らばっていて、男の子とその家族も見あたらなかった。ガードマンも事務所の人もいない。僕も何もなかったような顔をして、人の流れに紛れ込んだ。