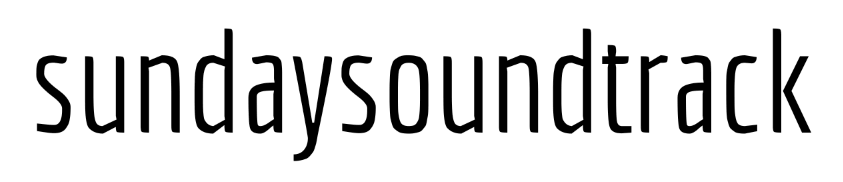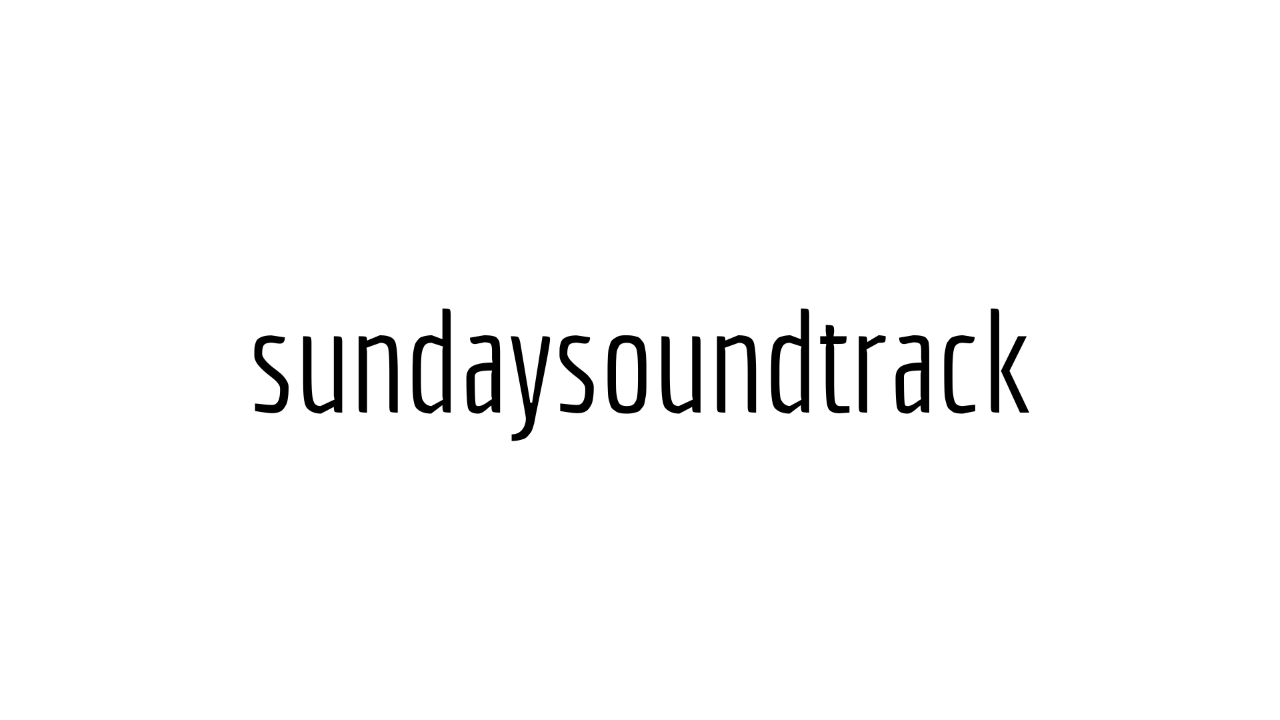そこは港町だった。良くも悪くも「おっさん臭い町」だった。僕の住んでいたマンションからすぐのところに船寄せの港があり、昼過ぎになると漁船がカモメと共に帰ってきた。風は常に湿気ていたし、髪は少しベトベトした。
不定期にもらえた休みの日は、基本的にあまりやることがなかった。仕事仲間となかなか休日が重ならなかったというのもあるし、一人で休日にどこかに出かけようとする気力があまり生まれなかったというのもある。少し気合を入れて東京に出るか、そうでもなければその辺をぶらぶらして一日を過ごしていた。
すぐ近くに、日本でも最大規模の超巨大ショッピングセンターがあった。そこで大抵の買い物はそこで済ますことはできた。ただ僕の仕事場もそのショッピングセンター内にあったので、なんとなく気分的にそこに行くのは嫌だった。毎日怒鳴られてはボロカスに言われていたし、なんだかいいことはほとんどない職場だった。だから休日になると、ショッピングセンターの端に位置するその職場を見たくもなかったので、その反対側の入り口からショッピングセンターに入っていた。かなり遠回りして。
ショッピングセンターに行っても、行くところはいつも決まっていた。本屋に入って本を立ち読みし、CDショップに入って新譜をチェックし、カジュアルショップや靴屋さんを覗いては買いもしない服や靴を眺めた。そしてダイエーのマッサージチェア売り場に行って、15分か30分ぐらいマッサージチェアに座るというのがいつものコースだった。つまらない人生の典型的な一日のようだ。いつ仕事をやめてもおかしくなかった。意気消沈した日々。
この港町に住んでいた時期に、コンパクトカメラを買った。一眼レフカメラを実家に置いてきたからだ。××市内かどこかのヨドバシカメラで2万円ほどで買った。そのニコンのコンパクトカメラを持って、よくその港町をぶらぶらした。11時ごろに起床して近くのラーメン屋で昼を済ませ、散髪をして、銀行に行って、それから日が暮れるまで歩いた。港町の漁船の「おっさん」は忙しいのか忙しくないのかよくわからない感じだったし、あまり町からあくせくした雰囲気は感じなかった。どちらかと言えば、空気は緩かった。漁船のエンジンだろうか、「ポンポンポン…」という長閑な音と、ときどき出くわす「落花生」の看板からそう感じたのかもしれない。
夜は近くの韓国料理屋で一人でビビンパとかを食べた。お客さんが一人もいないような店だったので、一人で切り盛りしている品のいいおばさんとはときどき世間話をした。僕がこの港町を離れるときには挨拶ぐらいしようと思っていたけれど、結局忘れてしまった。
四畳半の部屋には何にもなかった。布団と少しの服と簡単な荷物以外は、文字通り何にもなかった。ギターやパソコンはもちろん、本や机やテレビやラジオもなかった。部屋に張った一本の紐に、ハンガーに掛けた洗濯物が吊るしてあるくらいだった。部屋は12階だったので、高所恐怖症の僕はベランダに出られないのだ。
かろうじて携帯用のCDプレーヤーがあった。つまり部屋でできることは何もなかった。数少ないCDを聴くことと、考えること以外は何も。
真夜中に、マンションのすぐ近くの赤い橋でドラマのロケをやっているところによく出くわしたが、テレビがないので何のドラマかわからなかった。台風が来ていることもわからないので、「やけに今日は雨風が強いな」と暢気なことを言っていた日もあった。
この港町には2ヶ月住んでいた。ここで暮らしたことが、僕の中に何かを形成したことは間違いない。どちらかと言えば町自体は好きだったけれど、味のないガムのようなその頃の生活は嫌だった。だからこの町で買って延々と聴いていたCDは、今なかなか聴こうと思わない。カスタネッツ『パーク』、シング・ライク・トーキング『Welcome To Another World』、槇原敬之「素直」、中村一義『金字塔』、ザ・ブーム『THE BOOM2 (BLUE)』。なぜだか邦楽ばっかりだ。中村一義はあまりの閉塞感に手放してしまった。
これは1997年6月から7月いっぱいにかけての話である。
そのショッピングセンターにあった百貨店は、ついこないだ閉鎖された。僕が働いていたところがどうなったかは知らない。