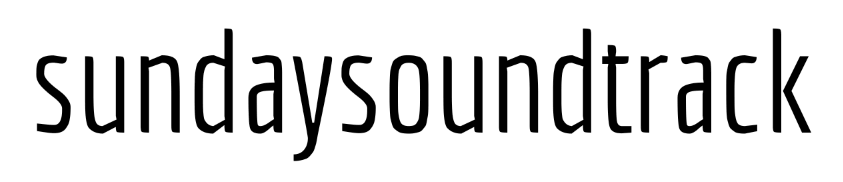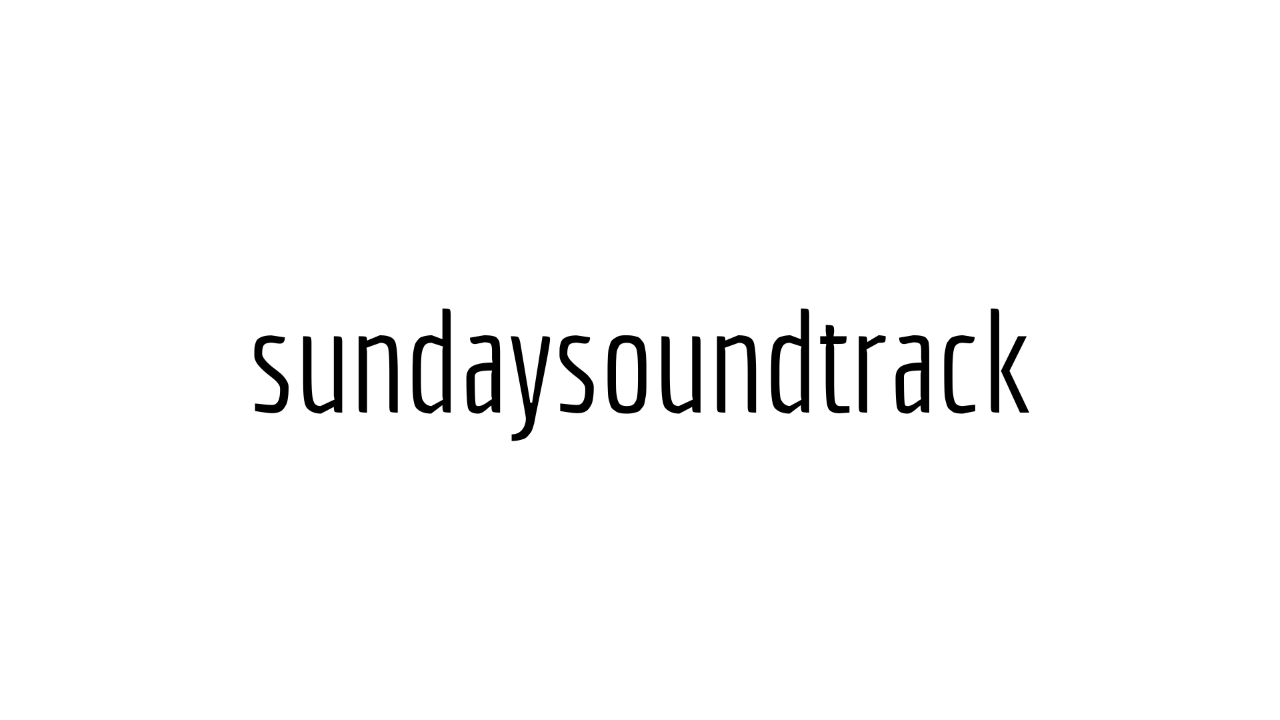「記念写真とか、ハイ・チーズとか言って撮るような写真って、なんかイヤ」と彼女は言ったことがある。「なんか、写真がわざとらしいから。みんなどこかしら何か作ってるから」
「うん。」と僕はそのとき少し間をおいて答えた。「確かにそうかも知れない」
僕も少なからずそう思うことはある。記念写真で撮られた僕の写真にまともなものはほとんどない。妙にかしこまっていたり、或いは作り笑顔だったり。でも記念写真のすべてが悪いわけじゃない。時には記念写真だって必要なときがある。そのとき誰が何処で何をどうしたかについて、そのほんの一欠片を写真は教えてくれる。たとえそれがありふれた記念写真であっても。
彼女は写真の勉強をしていた。彼女は写真学校に行くほど金銭的に余裕のある家庭に育たなかったので、高校を卒業してフリーターを続けた後、ちょっとした写真スタジオのカメラマンのアシスタントの仕事をしながらそこで写真を覚えていた。最初はアルバイトとして働いていたけれど、いつのまにか僕が知らないうちにそこの社員になっていた(彼女が言うには「いつの間にか社員にならされていた」らしい)。もちろんその写真スタジオの仕事の多くはいわゆる記念撮影的な仕事が多かったはずだけれど、彼女はそれについてはあまり多くを話そうとしなかった。彼女なりにそこに何か違うものを求めていたのかも知れないし、或いはそこから何かを掴もうとしていたのかもしれない。
おかげで僕と彼女が一緒に写った写真は実は1枚もない。ふたりでどこかに遊びに行っても、誰か見知らぬ人に頼んでふたりの写真を撮ってもらうなんてことは一度もなかったし、ふたり顔を寄せ合ってカメラをこちら側に向けてニカッと笑ったことだってなかった。彼女は中古ながらちょっとした一眼レフのカメラを持っていたけれど、撮るものといえば見知らぬ人や街の風景ばかりだった。たまに突然僕にもカメラを向けたことはあったけれど、きっと彼女は「僕」という匿名的事象(性別「男」)を記録しようとしていたのだと思う。その事象が僕である必然性はたぶんなかったはずだ。つまり「彼氏」としては写真の対象ではなかったということだ。
実は僕も中学の頃から写真をやっていた。もちろん彼女はそれを知っていた。僕は昔撮ったくだらない写真を見せたことがあったし、アドバイスを求められることだってあった。でも僕はそれほど本格的にやっていたわけじゃないし、僕の写真の幾つかについて彼女が誉めてくれる言葉を聞いても、ただ「ふーん。そうなんだ」という感じだった。彼女には悪かったけれど、僕は自分の写真における才能というものに全く自信はなかったのだ。
もちろん僕のカメラが彼女をとらえることも少なかった。僕が彼女に向けてレンズを向けたときに彼女がどう思うかを考えると、なかなか気が進まなかった。彼女は僕がレンズを向けても別になんでもない素振りをしたし、「別に構わないよ」と笑って言ったことだってあったけれど、なんとなく僕は遠慮した。結果として僕が撮った彼女の写真は数えるほどしかない。匿名的事象(性別「女」)として撮った写真も、「彼女」として撮った写真も。
—
写真に対する考え方の違いとは全く関係なく僕らはその後男女として別れ、僕は大学を卒業し、そして就職した。それでも毎年彼女から年賀状が届いた。彼女から年賀状が届き、僕はそれの返事を丁寧に出し、翌年僕が引っ越しをしたものの彼女からの年賀状は転送されて届き、また僕は返事を書き、そういったことを繰り返しながら、まるで僕等の写真における考え方の違いのような距離を保ったまま、静かな交信は続いた。彼女の文面から、彼女がまだ写真の勉強を続けていることはわかった。そして僕が元気でやっているかどうを心配してくれていた。
しかし、その交信は去年止まった。僕が返事に「実は事情があって仕事を辞めたんだ」と書いてからだ。その返事が交信に影響を与えたのかどうかは知らない。彼女の身の回りに何かが起きたのかも知れないし、或いは僕の返事に関係なくいい加減僕に興味をなくしたのかも知れない。とにかくそれ以来交信は途絶え、そして僕はまた何度目かの引っ越しをした。つまり彼女から僕に向けた交信の可能性は物理的にも低くなった。その数字を上げるには、僕側からのアクションが必要になってくる。そう、僕は彼女の住所を知っている。彼女がそこにまだ住んでいるとすれば。
—
今度は僕から交信を試みてみようと思う。交信が再び繋がれば、僕が船の航路を変えたことも報告しよう。もちろん彼女が写真を続けていればいいなと思う。僕が一番知りたいのはたぶんそれだけだ。
元気かな。